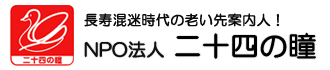だから国民が変わるしかないのである。変わるためには、真実を知ることが必要である。西洋医学を中心とする現代医学の限界について、わが国の矛盾だらけの医療システムについて、そして、健康を損なう原因を作ったのも、それをあるべき姿に引き戻すカギを握っているのもすべては自分自身のなかにあるということを、シニアだけでなく若い世代にも教えていくことが求められる。
借金大国になった日本にとって、医療費の増大は頭の痛い問題だ。医療費の財源は底をつき、医療保険制度崩壊も時間の問題だ。さらなる高齢化、しかも農薬や添加物まみれの食べ物で育った世代が歳を重ねていけば、医療費が青天井に増大したとしても不思議ではない。それに、ただでさえ少子化で、しかも環境ホルモンの影響でさらに子どもが減れば、働いている人たちが払う保険料は大変な額になるだろう。
それでも、病院や製薬会社が自らの利益を減らしてまで、予防に取り組むかどうかは疑問である。一方で、すでに厚生労働省は医療費の自己負担率引き上げにかかっている。このままでは、お金がないと医者にかかれない時代が来てしまうかもしれない。
本来は、それよりも医療費が毎年一兆円ずつ増えるのはどうしてなのかという真の原因を調べたうえで抜本的な改革をしないと駄目なのだが、これまでに述べてきたように、自らの利権が消滅するのを恐れ、真剣にこの問題に対峙しようとする人はほとんどいない。国民医療費適正化などと叫びながら、だれも真剣に適正化などしたくない。むしろ、ちょっとずつ増えていってくれた方がありがたいと思っているひとがほとんどなのではないか。そう思わずにはおれないほど、わが国には戦略がない。
現在病医院で行われている治療のほとんどは、症状を緩和する対症療法であり、原因そのものを解決するものではない。のべつ幕なしに処方される薬の副作用は国民にとっては大いなるリスクである。
しかしこの裏には、病医院は予防ではメシが食えないという事情がある。病医院や医者たちは、いくら病気の予防に力を注いでも儲からない。それどころか、逆に減収してしまうのだ。この点を患者側は認識しておく必要がある。
これには日本の医療制度が出来高制を敷いていることが影響していて、患者をすぐに治してしまうと収益が上がらないしくみになっているのだ。ダラダラと治さずに通院させたり、最初の処置がダメだったからといって別の処置を施したりするほうが儲かってしまうのである。
もし、高血圧や高脂血症やがんや糖尿病患者が激減すれば、医療関係者の懐には北風が吹き荒れることになる。だから病気の予防に本気で取り組もうとする医師は少ないし、医学部のカリキュラムにも予防医学は登場してこない。
その一方で、「治療より予防を」という言葉だけが一人歩きして、国は具体的なアクションプランを提示しない。ならばとばかりに、個人的に予防に投資しようとしたまじめな人たちが健康食品やらサプリメントやらの悪徳商法の被害者になってしまっているというのが現在の日本なのである。
今日のわが国医療の迷走ぶりは、理念なき医学教育や診療報酬体系の矛盾といった国家レベルでの戦略のなさがもたらした相乗的スパイラル現象なのである。 (続く)