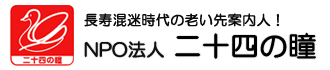お母さんの顔を覗きこむように声をかけると、心なしか瞳が潤んでいるように見えた。
「先生、いいお話をありがとうございました。なんか、私はダメな母親だったかも知れません。この子がハンバーガー食べたいと言えば、こころのどこかで、アッ、それならラクでいいな…って思っていました。家事をしているとき、この子がスナック菓子を食べながらテレビを観ていてくれると、仕事が捗って助かるな…って思っていたのです。」
「いやいや、みぃんな、いまのお母さんたちは忙しいですから。僕らの時とは時代がちがうんですから仕方ないんです。でも、その仕方ないというなかにも、ほんの少しでいい、無理はしないで、できる範囲でいいからひとつだけでも工夫をしてみて欲しいと思うのです。レトルトカレーでもいいです。でもちょっとサラダを添えてあげるとかね。」
「先生は、よそのお医者さんとはだいぶ違いますね。今日みたいなお話、誰にも教わったことはありませんでした。何か学校で授業を受けているような気がしてきました。」
「あっ、ごめんなさいね。ちょっと話が長くなっちゃいましたねぇ。」
お母さんはかぶりを振って、少しがんばってみる、と言ってくださった…。
医食同源という言葉がある。「食」という字は「人を良くする」と書く。本来は医療も食事も人を健康にするためのものであるはずだ。が、農業の方法が変わり、昔であれば田畑からの収穫物さえ食べていれば摂れていた栄養素が摂れなくなってしまった。おまけに、商業主義の象徴である身体に良くないジャンクフードの氾濫である。私たちは現在、昔は食べることがなかった食品を食べるようになってしまった。
ほんの30年前くらいまでは、どこの家庭でも火の通った和食が基本だった。ところが、急激な欧米化が進み、国の指導で今までに食べていなかった食品が主流になってしまった。しかし時が流れ、いまや欧米諸国がかつての日本の食事に学び、肉食中心の食生活を改めることにやっきになっている。それも国全体の取り組みとして、だ。
その結果、この20年、生活習慣病の代表であるがんで亡くなる人の数が減り続けている。人間は牛乳・肉・卵を食べなくとも生きていけるのだ。動物性食品は本来必要ないのだが、食べると身体がどんどん大きくなるので体格は良くなる。しかし、もともと必要がないものなので体質に合わない人もでてくるわけだ。
オリンピックのシンボルマーク「五つの輪」。あのマークは、ユーラシア・北アメリカ・南アメリカ・アフリカ・オーストラリアの5大陸を表わす輪が、秩序と調和をもって関係する様子を抽象化したものだ。一方、食の世界では、基本的な4つの味「甘み・酸み・塩み・苦み」があり、それに加えて、わが国に特有の「旨み」(昆布やかつお等から摂るダシの味)を加えて5味という概念がある。
私は、いまの子どもたちには、ものを食べたときの美味しさをじっくりと感じ取る努力が欠かせないと考えている。「あぁ、美味しい!」ではなく、「どう美味しいのか」、「この野菜はこんな味がするんだ!」、「化学調味料を一切使わない料理とは、今まで気づかなかった、こんな味がするのか!」…。こんな感じだろうか。こうしたひとつひとつの発見が、子どもたちに「食」の楽しさや、物事の道理を考えようとする思慮深さを与えていくのだと信じている。
そして、つぎに大切なのが、どのように食事を摂るのか、「食」とどのように接点を持つのか、ということ。今日では、「何を食べるか」のみならず、「どう食べるか」が置き去りにされています。欠食、早食い、ながら食い、立ち食い・・・。こうした悪習を正すとともに、食物生産のしくみ、流通のしくみ、生命の尊厳、地球環境への配慮、家族や親しい友人との絆…。現代人が忘れかけている大切なことを呼び覚ますことのできるような創意工夫を凝らしていく必要があるだろう。
その昔、日本の家庭では、毎日の食生活の中で、親から子へ、食に関わる基本を伝えることが自然にできていた。しかし今日では、核家族化や家族内での生活リズムの不一致から、食の知識・技術が伝承されなくなってきてしまった。
食は、健康、生活、精神にいたるまでの、生きるために必要な基盤である。食が乱れると、生きる力が損なわれてしまう。こうした食の乱れを正し、食の知識を引き継いでいくために必要なのが、ここ数年話題となっている「食育」の本質なのだと思う。
食育とは、食を通して生きる力を育むこと。正しい食習慣を身につけることは、単に望ましい食事をとることだけでなく、家族の絆を深め、自立した食生活を営むための基本的な力を育むことにつながるはずだ。
特に「食との関わり方」は、子どもたちの情操教育上、極めて有用だと思う。毎日の献立を決め、食材をそろえ、調理し、片づけを行うまでの一連の作業。こうした作業を行う中で、調理技術や、食に関する知識、マナーが身につき、それが「人が自立して生きていくための力」となるのである。
また、食物や食物を作っている人たちへの感謝の気持ちも芽生えるはずだ。子どものときに簡便な食生活しか体験していないと、このような食を通して身につけるべきことが、欠落してしまう恐れがある。それを防ぐには、親がまず、毎日の食生活を大切に思い、適切な食事作りを行うことが必要だろう。そして、食事作りに子どもたちを参加させるようにする。そして、一流ホテルの一流シェフが作ったような料理では決してなく、どこの家庭にも冷蔵庫を開けたら普通にある食材を使って、大切な家族のために、お母さんが真心こめて作る食事。つまり、家計にも優しくて、愛情もたっぷりの食事。
世のお母さん方が忙しいのは百も承知。でも、かけがえのない子どもたちのためである。「忙」とは心を亡くした状態。心ここにあらずで大切なお子さんと接することだけは避けて欲しい。心からそう思っている。
(完)