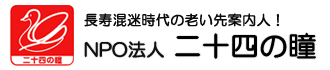帯津式統合医療モデル
先述したように、統合医療とは西洋医学と東洋医学とを上手く組み合わせた相互補完的な医療のことを言います。今現在の日本で、この統合医療でもっとも有名なのが、埼玉県川越市にある帯津三敬病院の理事長の帯津良一氏だと思います。帯津院長は東大医学部を卒業して以来、西洋医学や手術というものに限界を感じていたそうです。
そして、都立駒込病院で外科医長をやっていた時代についに決断して、中国に渡って本格的に中国医学を学び、1982年、自分の信ずる医療を行うため独立開院したのです。その帯津三敬病院では、西洋医学に中国医学、気功、瞑想、食餌療法、心理療法などを加味した総合的な治療法が実践されており、全国からがん患者さんたちが集まっています。そして、西洋医学で見放された患者さんたちが、免疫力を高めることで自らの自然治癒力を取り戻していかれた数多くの事例を提供しています。
「治療の決め手は患者さん自身のなかにある免疫力を引き出すこと」と、帯津院長はたくさんの著書を通じて発信しています。そして、免疫力を引き出すためにもっとも大切なのは患者さんの心だと言います。病状を改善するには、どんな薬よりも充実した心でいること。そのために病院が提供する気功などの心理療法に参加してもらうようにしているそうです。
心のつぎに大切なのが食事です。病院で出す食事は玄米食が中心といいますが、あくまでも基本は自宅での食生活にあるとして、管理栄養士の指導の下、食事に対する考え方と具体的なレシピについてしっかり身につけてもらうようにしているとのことです。
帯津三敬病院には、初診のがん患者さんだけで、年間に1000人近くが訪れてきます。帯津院長は、カルテと紹介状に目をやりながら、膝詰めで対話するように統合医療の考え方や、同院の治療方針を説明します。がん治療の基本は免疫力を高めることです。そのために、まずは精神の高揚が大事であること、つぎに免疫力を高める食生活を徹底することなど。
これらひと通りの指導を行った上で、手術したほうがいいのか、それとも化学療法剤や放射線療法を行ったほうがいいのか、漢方・鍼灸・健康食品をどの局面で組み込むようにするのか等々について、患者さんやご家族の希望を聞き入れながら治療方針を決めるそうです。「医師と患者が手のうちを見せ合って一つの結論を出して行く」(帯津院長)手続きがあって初めて患者も納得し安心すると仰っています。帯津院長の考え方に触れて、私がクリニックで行っているやり方とまったく同じなので、非常に嬉しく感じたものでした。
2009年11月21日に高野山で行われた『21世紀医療フォーラム』で、帯津院長はさらに興味深いお話を披露してくれました。「開業して以来、これまでにカルテを作った患者の約7割ががん患者。がん患者の改善例を総合的に分析してわかったことは、症状が改善するかどうかは患者の精神状態に依るところが極めて大きいということ。前向きな人ほどNK細胞も活性化しやすいが、マイナス思考の人はどんな治療を施しても良い結果が得られない。当院ではできる限り多種多様の治療を取り入れていて、精神状態が安定し、がん抑制効果が表れる患者さんは、自分はこれだけのことをやっているんだという自信や達成感が裏づけとなっている」ということでした。