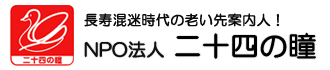がんの摘出手術について、最初に問題提起をしたのは、慶應大学病院の放射線科の医師である近藤誠氏だと思います。1995年に出した『がんは切ればなおるのか』(新潮文庫)で、好感度の高かったアナウンサー逸見政孝氏とニュースキャスター山川千秋氏を例にとって、がん手術の有効性に疑問を投げかけたのです。当時はとても衝撃的な内容で、医療界全体を巻き込んでの大論争となったものです。その後も何十冊という著書が出されていますが、近藤氏が一貫して訴えているのは、「がんの手術はするな」、「がん検診は不要」、「抗がん剤は効かない」、「患者本人に告知せよ」の4点です。がん恐怖症に陥りかけていた世の中に、「もしかしたら手術をしない方がよいかも知れない」という時代の雰囲気をもたらした功績はとても大きかったと思います。
当時はまだ、今ほど医師という人種の権威が地に落ちてはいなかった時代です。患者さんからすると、医師が手術だと言えば、それは当然自分を助けるために言ってくれているものだろうという先入観がありました。しかし実際には、患者さんをモルモットがわりにして論文を量産するために行われた手術もあったかもしれません。そのことを世間に知らしめ、医師の言うなりになることなく、自衛のためにも勉強すべきだと啓発した意味は計り知れません。あれ以来、確実にがん患者さんやご家族が、がんというものについて情報収集したり、医師にいろいろと説明を求めたりする習慣がついてきたように感じています。そしてこれは、これから医療が健全に発展していくためには非常に価値のあることです。
かつて結核をはじめとする伝染病や、栄養不良に起因する外来性の病気に有効だった「早期発見・早期治療」という方法論は、がん、脳卒中(脳血管患)、心臓病など、今日的な生活習慣病には必ずしも通用しないという考え方が世界的に広まってきています。何といっても、がんによる死亡者数が毎年増え続けている事実が、結局「早期発見・早期治療」が逆効果になっていることを証明しているではありませんか。適切な検診や適切な治療が行われているならば、がんで亡くなる人たちの数は徐々にでも減少してきていいはずですからね。
なのに日本では、がん対策として“早期発見・早期治療”とあちらこちらで盛んに謳われています。しかし、こういった世間では常識とされていることほど疑ってみた方がいいのかもしれません。例えば、自治体などで盛んに喧伝されている集団検診。私が思うに、そもそも集団検診で見つかるようなレベルまで大きくなったがんは、もはや早期発見とは言えません。仮に、PETなど云億円もする高価な検査機器で些細な腫瘍を発見したとして、現在のがん治療では摘出手術と術後の抗がん剤および放射線治療という流れが一般的です。
しかし、こうした従来の治療法では免疫系をかなり抑制してしまうことがわかっています。患者さんの身体を衰弱させ、生きようとする意欲や心身の活力を萎えさせてしまうのです。がん自体が多少小さくなったとしても、全体として良い結果が出ないケースがたくさんあるのです。つまり、いくら早期発見をしたからといって、治療法の選択を誤ったのでは意味がないということです。無理やり見つけて、なんでもかんでも抗がん剤や放射線で治療しようとしたら、何もせずに放っておくよりも危険な場合が多いのです。ここらあたりの事情について、医師のみならず患者さんも理解することが必要だと思います。化学物質や放射線で身体を痛めつけて病気が治ると思うほうがおかしいと思いませんか。
いまや国民の2人に1人ががんで死ぬ時代です。患者さん側も情報武装する必要があるでしょうが、医師のほうも真のプロフェッショナルならば、何も治療しないということも含めて、がんには手術以外にも選択肢があるということをわかりやすく示さなければならないと思います。たまたま入局した医局が提唱する治療法に固執するだけで、自身が学んでいないからといって別の治療法を頭ごなしに否定するのではプロ失格と言われても仕方ないでしょう。
そして患者さん側も、そんなプロ失格の医師が多いという前提で自ら学ぶことが必要です。自分を守るのも、健康にするのも、医師ではなく自分自身であるという真実をしっかりと認識しておくべきなのです。