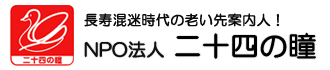患者不在の延命治療
西洋医学は救命と延命を第一の目的とする医療です。従って医師たちは治癒の見込みのない患者を相手にするのが得意ではありません。1950年代から急増し始めたがんは、症状が厳しく、死に至る病として忌み嫌われてきました。がんの病巣が発見されると、可能な限り広範囲にわたって臓器を摘出し、その後も抗がん剤や放射線でがんを叩き潰そうとしました。しかしその結果、患者さんたちはみな、苦痛と疑念、孤独と絶望の中で死を迎えました。私自身、いま振り返ってみると胸が痛む思いです。
不治または末期で死が目前に迫っている患者さんには、さまざまな精神的苦痛(今日ではスピリチュアルペインと言われています)が襲いかかります。もう何をしてもムダだという絶望感や虚無感、誰もわかってくれないという孤独感、死という未知のものへの不安や恐怖などでしょうか。こうした、死ぬことで自分の存在や意味が消滅することによる苦痛は、多くの患者に共通して現れるものです。
しかし、こういうものに対して今日の西洋医学は配慮しなかったし、手を差し伸べようともしてこなかったのです。それどころか、医療技術の進歩によって死や命を操作することまでしてきました。その際たるものが延命治療です。西洋医学にはこれまで延命を第一の目標として進歩してきた歴史があります。医師たちはもうだめだとわかっていても、自然の摂理に反してでも命を長引かせる努力をすることで明日の医学が生まれると教えられてきたのです。
一方の患者さん側も、患者さん本人が自然に任せて天寿を全うしたいと望んでいても、家族の意向で不必要かつ無意味な延命措置につき合わされてしまうようなところがあると思います。「意識は戻らなくてもいいから一分一秒でも長く生きていて欲しい」というご家族がよくいらっしゃいます。しかし、患者さん本人の苦痛は半端なものではないと思います。人工呼吸器を取り付けるということはどういうことを意味するのか。医師はきちんと説明しなければいけないし、患者さん側も普段から理解しておくようにしたほうがいいと思います。
患者さんが亡くなったとき、「できる限りのことはしました」と、よく医師は言います。ご家族も、「できる限りのことをしてあげてください」と頼みます。しかし、医師やご家族にとってのベストが患者さんにとってのベストとは限らないということを知るべきです。もう元の生活には戻れないということが明らかになったとき、患者さんがどのような最期を望んでいるのか。そこを事前に共有したうえで事に当たって欲しいのです。
ただ、延命治療については、実際に家族がそのような状況になってみると判断が揺らぐものなのだというのも真実かと思います。というのは、昨年、諏訪中央病院院長の鎌田實氏のお話をうかがう機会がありました。鎌田氏といえば当然たくさんの延命治療に携わっているわけですが、講演のなかでもっとも印象に残ったのが、鎌田氏自身がお母さまに延命治療をするかどうかという場面になったときの話でした。
鎌田氏はお父さまに「延命治療をやめよう」と言いました。するとお父さまは、「バカもの。医師の務めは最後まで尽くすことだろう」と一喝されたというのです。それまで一度もお父さまに怒られたことはなかったそうです。で、結局鎌田氏は、意に反して父親の言葉に従ったと述べておられました。正直で誠実な人柄が滲み出るようなお話でした。医療のプロであってもこうなわけです。いくら経験の多い医師であっても答えはひとつではないのです。一般の人たちが思い悩むのは当然のことだと思います。