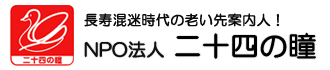狐狸庵山人からの宿題
さて、延命治療のことを考えるとき思い出すのが、狐狸庵先生こと遠藤周作さんのことです。彼は、1996年の秋に肺炎による呼吸不全で亡くなられました。それから3年くらいして、奥様である遠藤順子さんの講演を聞く機会がありました。テーマが『心あたたかな医療』ということだったので、何となく聞いてみようかなぁと、そんな軽い気持ちでした。
遠藤周作さんは、1980年代の半ばから『心あたたかな医療運動』というのを提唱して活動していたそうです。ご自身がいくつも大病を経験されていたということもありますが、直接のきっかけは、20歳代半ばにして骨髄がんで逝かれた遠藤家のお手伝いさんの死ということでした。当時、蓄膿症の術後だった遠藤さんは、上顎がんの疑いありということで、彼女と同じ病院に入院していました。敬虔なクリスチャンだった遠藤さんは、余命いくばくもないお手伝いさんのために、せめて安楽に死を迎えられるよう1ヶ月のあいだ祈り続けました。愛煙家であった彼が禁煙までして…。
そして彼女の死後、上顎がんの疑いが晴れた遠藤さんは、延命治療のあり方や医師の無神経な言動に疑問を抱き、「心あたたかな医療運動」を思い立ったといいます。お手伝いさんが死にゆく過程、遠藤さんご自身の入院経験(亡くなられる数年前にも腹膜透析の手術で長期入院されていた)などを通じて問題意識があったようです。遠藤さん亡き後は、奥様がその遺志を継いで活動しているとのことで、私が聞いた講演会もその一環であったことが後でわかりました。
講演のなかで奥様は、「事後承諾で人工呼吸器をつけられ、亡くなる日まで一日に何度も採血をされ、腕は青く腫れ上がりました。さいごは、機械のゴーゴーいう空襲のような騒々しさのなかで、主人とは最後の言葉ひとつも交わせずに逝ってしまいまし。本当にあんな終わり方で良かったのか、今でも心残りでなりません」と訥々と語り、「今、病院で医師の正義に最後まで付き合わされる患者がたくさんいます。しかし、現代の医学が効力を発揮できなくなった時点で、もう医師と患者という関係は切れていて、あとはもう人間と人間の関係だと思うのです。患者と家族が心静かに別れることができる医学的な環境を整えてくださることも、ターミナル医療に携わる医師に課せられた役割とは言えないでしょうか」と結ばれました。
自らのつらい体験から、「心あたたかな医療運動」では、医療者に求めること、患者側も医療について多少なりとも学んでおくことを提唱しておられます。奥様は最初、どうして死の間際に苦しんでいる人から再三血液を採るのかわからなかったといいます。この採血は、血中の酸素濃度を測定し人工呼吸のレベルを加減するため、医学的に必要な処置ではあります。しかし奥様の心情としては、だったらひと言、なぜ「おつらいこととは思いますが、どうしても医学的に必要なことなのでご容赦ください」とでも言ってくれないのか。そんなやるせない気持ちだったのではないでしょうか。「医学的に当然のことをしているまで、みたいな顔をされるとしたら、まったくもって憤りを感じます」とそれはそれは強い口調で仰っておられました。
おそらく医療関係者は、患者さん側の痛みや苦しみに対して鈍感になってしまっているのだと思います。毎日重篤な人たちのなかで仕事をしていて、すべての患者さんひとりひとりにそんな気を配っていられないという部分もあるかもしれません。患者さんやご家族にとって病医院とは非日常的な場所ですが、医師や看護師にしてみれば何の変哲もない「日常」なのです。しかし、私自身が患者になったことを考えると、例え演技でもいいから悲嘆に暮れる人たちに寄り添うような言動を心がけて欲しいものです。患者さんが亡くなることや、家族が悲しむことに慣れっこになってはならないなと、再認識させられました。