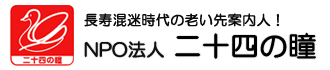死の準備教育
この章では、生きとし生けるもののすべてが迎えねばならない『死』というものについて、西洋医学と東洋医学の捉え方のちがいについて考えてみたいと思います。私も含めて医療に携わる者たちが『死』とどう向き合うべきかを考えるきっかけをもたらしてくれた偉大な人物が3人います。
英国の内科医で現代ホスピスの創始者であるシシリー・ソンダース博士。彼女は1967年に自らの病院にホスピス病棟を開設し、その活動は全世界に広がりました。日本では80年代になって、淀川キリスト教病院や聖隷三方原病院などにホスピス病棟が開設されました。
スイス出身の精神科医であったエリザベス・キューブラー・ロス博士は、人間が死を受容するまでの心理状態の推移を1969年に『死ぬ瞬間』のなかで体系的にまとめました。これは現在でも全世界の終末期医療における指針となっています。
上智大学の名誉教授でアルフォンス・デーケンさんというドイツ人の司祭がいらっしゃいます。2009年まで、東京と大阪で『生と死を見つめる会』というのをずっと続けてこれらました。彼が1980年代初めに提唱した「死生観・死の準備教育」は、今日の病医院における医療や看護のあり方に変革を求めるものでした。
特にデーケン教授の活動は、彼が日本を活動拠点としていたことで多大な影響を及ぼしました。その最大の功績は死をタブー視する日本社会に大きな風穴をあけたことです。日本では昔から死は穢れの対象とされ、不浄で忌むべきものとされていました。かつてのハンセン病のように、がんと宣告されるとそれは人間社会の外側に放り出されることを意味するようなことがあったのです。いや、場合によっては現在でもそんな部分が残っているかもしれません。デーケン教授は、人間社会の枠の外に置かれていた死というものを、人間社会のど真ん中に引き戻してくれたのです。そして、死とは生を照らし出す鏡であることを私たちに教えてくれたのです。