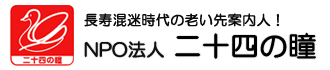病医院の昨今の経営環境は非常に厳しいため、予防だの早期発見だの言って、ことあるごとに検査を勧めてくるはずだ。ろくに診察もせずに、とりあえず検査という医者が少なからずいるだろう。今日では、いまや人間ドックをふくめ検診業務は医者にとって貴重な収入源。とくに日帰り診断・治療が可能な内視鏡は稼ぎ頭だ。そこには、検診自体による収入があるばかりでなく、検診で発見した病気を治す過程でまた儲かるという一石二鳥の構造がある。
●普通の医者 「とりあえず検査しておきましょう」と言って、患者に同意を求める。コスト削減のため、たまに無資格者にレントゲンを撮らせていたりする。検査スタッフに疑問を抱いたら、「失礼ですが、あなたはレントゲン技士さんですか?」と尋ねてみること。検査結果については、一般の標準値と比べるだけで、患者個々の遺伝体質・生活歴・病歴までを考慮することはない。少しでも標準域を外れると、薬でコントロールすることを勧め、そそくさと処方箋を書き始める。
●良い医者 本当に必要な最低限の検査しかやらない。検査を勧める場合には、いまその検査を受ける必要性や目的、検査の具体的なやり方、検査前投薬の有無と副作用リスク、検査後の注意事項についてきちんと説明してくれる。検査結果についてもきちんと説明の時間を取ってくれ、生活指導を行ってくれる。過去の検査データ等を持参すれば、患者個々の遺伝体質・生活歴・病歴等を考慮して結果を判読してくれ、一般の標準域を外れたからといってすぐに薬を勧めたりはしない。検査所見を紙に書いてくれることもある。
●悪い医者 とにかく検査を執拗に勧める。健康オタクだとわかれば嬉々として高額な宿泊滞在型人間ドックのパンフレットを取り出してくる。数値データを取ること(あるいは、収益を上げること)だけが目的であり、特に説明や解説はしない。異常値やグレー値に対して可能な限りの薬を処方する。もちろん、継続して定期的にさまざまな検査を受けるよう勧めることも決して忘れない。こういう医者に限って、もっともポピュラーな胃の検査では、胃カメラの消毒を怠っていることもあるから要注意。
病医院を経営する医者の立場になってみれば、病人や病気が減っては都合が悪いのは当然だと理解できるだろう。そうかと思えば、PET検診を目玉にしたリゾートツアー等の高額な旅行商品が流行ったりもしている。こうしたものに投資する人たちを否定する気はないが、検査を受ける側には絶えずリスクがついてまわるのだという認識だけは持っておいて欲しい。自分の病気を正しく理解し適切な治療を受けるためにも、医者がその検査で何を知りたがっているのかを明確に聞きだす必要がある。
<ワンポイント・アドバイス:知らなきゃ怖い検査のリスク>
検査といっても幅広いが、検査前の投与薬には副作用、造影剤にはアレルギーやショック反応、内視鏡等による穿刺には血管・臓器・神経等の損傷リスクが想定される。また、検査に用いる器具の消毒不備による感染症リスクも侮れない。これら危険因子が二つ以上あるものをリスク大、ひとつのものをリスク中として分類すると以下のようになる。
<検査別のリスク分類>
リスク小:血圧測定、心電図、尿検査、視力検査、眼圧検査、眼底検査、肺機能検査、X線検査(造影剤なし)、CT検査(造影剤なし)、MRI検査(造影剤なし)、腹部超音波(エコー)、血液検査、生化学検査、血清学的検査、胸部・腹部等の単純レントゲン検査
リスク中:X線検査(造影剤使用)、CT検査(造影剤使用)、MRI検査(造影剤使用)、注腸造影検査(下部消化管X線検査)、関節造影検査、負荷心電図、腎盂造影検査、胆嚢造影検査、脊髄穿刺
リスク大:胃透視造影検査(上部消化管X線検査)、胃内視鏡検査(胃カメラ)、大腸ファイバー検査(下部消化管検査)、膀胱鏡検査、関節鏡検査、気管支造影検査、肝・膵・腎の生体検査、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査)、羊水穿刺、脊髄造影検査、脳血管造影検査、心臓カテーテル検査、冠状動脈血管造影検査