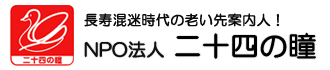結婚について
結婚。それは、いかなる羅針盤もかつて航路を発見したことがない荒海。結婚とは二人のエゴイストの共同生活に他ならない。これをかろうじて相互に妥協させ許し合わせるものが、当初にあったところの愛着である。愛する者同士の結婚ならば、結婚後に露出されるエゴやわがままを我慢するだけの愛着がしばらくは維持される。愛情とは結婚生活において育まれるものではなく、愛情が両方にある場合だけ、お互いの醜さを耐えるだけの我慢を持つことができるのだ。
要するに、愛の貯金を食い潰していくプロセスなんだよな。だから当事者のうちの一方が相手に対する憐憫の気持ちからする気になった結婚は不幸なもの。そもそもが愛してない相手の、日ごと表れる醜い部分を消化しきれない。結婚の課題は、何よりも生活していくこでと、実はこれには必ずしも愛を必要とはしない。
愛の死滅後に始まる共同生活に必要となるのは、一に生活力。二に人間としての聡明さ。三に妥協の技術。そして生活力とは、間違っても愛の果実などでは決してない。価値観の相違からくる二人の間の溝を、愛の寛容で忍耐を重ね、長い年月をかけて埋めていくのが結婚という作業である。人格も性格も異なる二人が、どこまで相手に順応できるか、歩み寄れるか、努力するのが夫婦の共同生活だ。自分からは相手に順応しようとせず、なにがなんでも相手にこちらへ来いと歩み寄りを強要する夫が悪夫であり、妻が悪妻と呼ばれる。
夫婦は独立した個人と個人の共同体。互いに別の世界を持っていて当然だ。相手の世界を認め、いかなる事態になっても立ち入ってはならないと心に決めておけば、そこが時として生じる摩擦や衝突の緩衝地帯の役割を果たしてくれるだろう。そうした人間関係を成立させるためには、お互いに対等な人間として認めあい尊敬しあわなければならない。生まれた場所も育った環境もまるでちがう男女間に、完全なる価値観の一致を期待するほうがそもそも無理。これを一致させようなどと考えると、ひずみが生まれ次第に大きくなり、やがて埋めがたい亀裂となる。
愛が消失した夫婦が営む冷えきった家庭に育つ子どもほど不幸なものはない。いかに心の離れた夫婦でも、子どもを育てるためだけに一緒に暮らすべきだという意見には賛成できない。愛なき夫婦間に育つ子どもの不幸を少しでも早く、少しでも多く償うために離婚すべきではないか。
夫と妻の心身のつながりがなくなり、それを再び求めることが不可能になったとき、一緒に生活する苦痛ほど人間を傷つけるものはない。その苦しみから一組の男女を救うのが離婚である。果たしてどちらに離婚の責任があったのか。どちらにもあったのだ。
男は女によって生きてくる。女は男によって生きてくる。女を女らしくできないような男は男じゃない。男を男らしくできないような女は女じゃない。