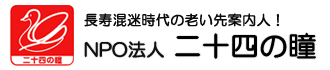薬売りと化した医者たち
さて、高齢者と薬の関係についてですが、もっとも重要なのが、人間歳を取れば必然的に臓器の働きは弱くなるという心理です。例えば肝臓の機能が落ちるということは、口から飲んだ薬を肝臓で分解するスピードが遅くなるということを意味します。腎臓の機能が落ちるということは、薬が腎臓から排泄される速度も落ちるということです。さらに、歳を取ってくると身体のなかの水分が減って油分が増えてきます。ほとんどの薬は油に溶けるため、体内に薬が溜まりやすくなることも考慮しなければいけません。
そうするとどういうことが起こるでしょうか。ふつうは薬を飲んで30分後ぐらいに、血中濃度のピークがきます。ピークがきてから何時間後に濃度が半分になるかという時間を「血中濃度の半減期」と言います。本来であれば、患者さんの年齢や遺伝体質や既往症等からこの「血中濃度の半減期」を判断して薬の処方量を決定すべきなのです。
たとえば、セルシンという名前で売られている「ジアゼパム」といういちばんありきたりの精神安定剤の場合ですと、この「血中濃度の半減期」が非常に長いという特性があります。濃度が半分になるのに、20歳代でも20時間かかり、恐ろしいことに70歳代になると70時間もかかるのです。つまり、あまり頻繁に飲んではいけない薬だということです。
一般に、歳を取ると殆どの薬は「血中濃度の半減期」が若い時の2倍位になります。ということは、高齢者が1日3度も飲むと薬が溶けるよりも、体内にどんどん溜まっていってしまうわけです。ですから、歳を取れば、薬を3度飲むのを2度にするとか1度にするとかにしてうまく調節していかないと、体内に化学物質である薬が蓄積されて、思わぬ落とし穴に嵌ってしまうという危険を孕んでいるのです。
こうして高齢者に対する薬の処方のあり方を見直してみると、本来、高齢者が増えれば増えるほど薬剤費は安くなっていくという理屈になりますが、わが国のほとんどの医師たちはこのようなことを真面目に考えていないか、あるいは売上を上げることしか考えていないか、今日も何種類もの薬をもらうために通院を強いられる高齢者たちが後を絶たないのです。
とても大切なことですのでまとめておきます。薬は飲まないに越したことはない。なぜなら、歳を取ると肝臓の機能が落ちて薬を肝臓で分解するスピードが遅くなる。歳を取ると腎臓の機能も落ちて、薬が排泄される速度も落ちる。歳を取ると体内の水分が減って油分が増えて、薬が油に溶けて体内に溜まりやすくなる。そうすると体内に溜まった薬が思わぬ悪さをしかねない。だから薬の飲みすぎは身体に悪い…ということになります。
ところで、先述したように、患者さんが知っておくべきなのは、そもそも医療には限界があるということです。患者さんだけでなく、医師もこの事実から眼をそむけてはいけません。私たちの健康寿命を決定する因子の半分は食事・運動・喫煙などの生活習慣です。他に、人間関係や住まい方などの環境が20%、生まれつきの遺伝子が20%といったところです。つまり、薬を含めた医療の影響はわずか10%に過ぎないのです。それではなぜ医師はたくさんの薬を出すのでしょうか?
実を言うと、診療報酬のマイナス改定が前提となった昨今では、これまでと同じような医療活動をしていたのでは当然減収となり、採算を度外視していたのでは病医院の経営は成り立たないのです。その結果、収益を上げようと、ちょっとしたことで検査したり、薬を必要以上に出したり、過剰な手術や終末期医療などが目立ってきたとしても不思議ではありません。今の制度では、診察するだけではさしてお金にならないので、とりあえずいろいろやっておこうということが罷り通っています。いまや医師たちは、薬と検査を売る商人…。そんな傾向は否定できないでしょう。