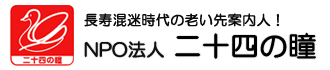刮目せよ
まぁ、随分ひどいことを言うものよねぇ。
そんなお叱りを受けそうだが、実はご本人たちも自覚があるらしい。
ここに、私たちが昨年(2010年)の初詣客に行ったアンケート結果がある。
質問は、『初詣でひとつだけ願かけするとしたら、それは何ですか?』。
①認知症になりたくない 30票
アンケートの対象は、東京都府中市にある大國魂神社に参拝に来られた65歳以上の男女150人である。
この結果から明らかなことは、一般的なお年寄りの願いとは、不安や苦痛から逃れることに対する欲求(①~⑤)の方が、楽しみや喜びを求めることに対する欲求(⑥~⑩)よりも圧倒的に強いということである。
そして、彼らの言う不安や苦痛とは、「認知症・寝たきり・要介護・老醜化・がん」であり、こうした悪夢のような状況に、すでに自分たちが少しずつ歩を進めているという自覚がある。このアンケート結果は、そう見て取ることができると思う。
しかし、元来、人間とはなまけものである。だから、元旦などの特別な日には改まってこうした願懸けをするのだが、「認知症・寝たきり・要介護・老醜化・がん」にならないための工夫や努力を日々の生活の中で行っているかというと、それはもう聞くまでもなくNOなのである。
そんな虫のいいお年寄りは、かなりの確率で悪夢が現実のものとなる。「認知症・寝たきり・要介護・老醜化・がん」にならないためにはどうすべきか。このことを真剣に考えることから逃げてきた罰が当たるわけだ。
●目尻のシワやシミ ●身体のシミ ●抜け毛 ●物忘れ ●話がくどくなる ●トイレが近くなる
●加齢臭 ●歯が抜ける ●姿勢が悪くなる ●動作が鈍くなる ●口臭がキツくなる ●体型が崩れる