感動する医者の話17
今朝最初の患者さんは、50代半ばの女性です。県立医大で数ヶ月前に子宮がんを告知されていたそうです。診察室へ入るなり、堰を切ったように喋りだしました。
「先生にお目にかかれて本当に助かりました。危うく命を落とすところだったんですよ。いえね、それがかかりつけの診療所の検診でひっかかりましてね、県立病院で精密検査を受けたら子宮体部のがんだっていうんですよ。わたしも何となく予感めいたものがありましてねぇ、いろいろ独学ではありますけど情報を集めて勉強はしていたんですよ。それが先生、2週間後に来いって言うからいったらあなた、もう手術のスケジュールが決まっているんですからね。いゃあ、もうびっくりするやら笑っちゃうやらですよ。なんてったって本人の私も知らないうちに手術の日取りまで決められちゃってるってんですからね。わたし、言ってやりましたよ、その仁丹やら龍角散やらみたい気難しそうな顔した年配の医者なんですけどねぇ、わたしはまだひと言もこちらで手術するなんて言った覚えはありませよってね・・・」。
本当に威勢のよろしい女性で、とてもがんの告知を受けた患者さんとは思えなかったです。しかし、彼女のようなケースは、決して珍しいことではないのです。私の診療所には西洋医学の世界で見放されてしまったり、術後の生活の苦痛に耐えかねて救いを求めてきたりされるがん患者さんがたくさん来られますが、それと同じくらい相談が多いのが、ほとんど何も説明のないままに、「一刻も早く手術して摘出しましょう」と押し付けられたことへの不満なのです。
このことは、現代の西洋医学において、がんの治療法がまだまだ旧態依然とした“手術ありき”であることと、インフォームド・コンセントが徹底されていないことを如実に物語っています。わたしは、勢いよく話し続ける女性をなだめるように、まぁまぁと言って尋ねました。
「ところで、がんであることを告げられたときの様子を思い出して聞かせていただけませんかねぇ?」
「様子もなにも、『あ、やっぱりそうですねぇ。まだステージIですから大丈夫です。とにかく2週間後にもう一度来て下さい』。そんで終わりですよ。病状の説明もなけりゃ、治療法にはどんなのがあるかの説明もない。なんですか、あれは?」
「はぁ・・・。本当にそれだけで、次に行ったときには手術の日程が決まっていたのですかぁ?」
「そうなんですよぉ、あんまりにもひどい話じゃないですか、先生・・・」
と、あんなに威勢のよかった女性が、突然しくしくと泣き始めたではないですか。
(続)
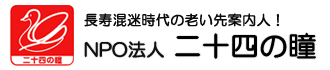

トラックバック URL
コメント & トラックバック/ピンバック
コメントはまだありません。
コメント