感動する医者の話5
さて、そしてやがて、最期のときがやってくる。比叡山が雪化粧をしはじめた頃のことだ。彼の危篤状態を知らせる電話が奥さんから入ったのは、夜10時過ぎのことだ。私は手早く準備をして、神戸に向けて車を走らせた。いつしか舞い始めた風花が、先を急く心を妨げた。彼が待つ病院に到着したのは、ちょうど日が変わるかどうかといった頃だったように記憶している。集中治療室に入れられた彼とどうにか対面することができた。
後に奥さんから聞いたのは、彼が私の到着を待っていたのだと思う、ということ。いつ逝ってもおかしくない状況が数時間続いたのだという。それは医者冥利、というか、一個の人間対人間の関係として、非常にありがたいことだ。最後の最期まで私を信頼していてくれたことの証のように感じられて、素直に嬉しく思う。
ベッドに横たわる彼の頬は痩せこけ、以前の彼とは別人のようだった。奥さんが眼鏡をあてがうと、瞳がゆっくりと左右に動き、やがて私のそれとピタリ重なった。私は両の眼に力を込めて、全身全霊で彼の瞳を見つめながら、力なく宙を彷徨う掌を握りしめた。
「●●さん、来たよ。来ましたよ。連絡をありがとう。2年間もの間、よぉくがんばりましたねぇ。すごいがんばりました。ありがとう。本当にありがとうございました。」
私の声が届いているのかどうか。瞳が頷いたような気がした。1分か2分のことだろう。息を呑むような静寂のなか、やがて彼の瞳は私と奥さんの間を行き来するようにして、そしてそっと顎が落ちたのだった。私は心のなかでそっと手を合わせた。ここから先はご家族だけの時間である。他人が居続ける場ではない。私は奥さんに黙って頭を下げ、もう一度彼に話しかける。
「ご苦労様でしたね。見事でしたよ。本当にお疲れ様でした。ぐっすりと休んでくださいよ。ありがとうございました。さようなら。」
心のなかで彼に敬礼し、集中治療室を出る。歩き出した廊下に、奥さんやご親族の泣き崩れる声が響いている。こういう場面は、何度体験してもつらいものだ。そしてやるせない。心のなかのどこかに、この私だって彼の命を救えなかったのは一緒ではないかという痛惜の想いがくすぶっているからだ。外に出ると、寒々とした蒼月が白く霞がかっている。大津への夜道を引き返しながら、私は彼と共有した時間をひとつずつ手繰っていった。
(完)
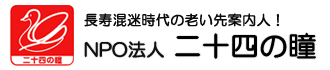

トラックバック URL
コメント & トラックバック/ピンバック
コメントはまだありません。
コメント