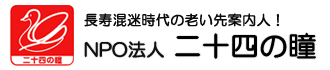【女性自身3/30号より】がん治療について
がん名医が末期がんに…それでも「治療しない」と語る理由
「誰にも言っていませんが、余命は1年もないでしょう」と自らの余命を語るのは、神戸市「新須磨リハビリテーション病院」院長の神代尚芳医師(67)。これまで約200人のがん患者を看取ってきたという神代医師。そんな彼が今、末期の肺がんに侵されているという。
がんが見つかったのは、昨年5月のこと。手術は、親友の医師により7月に行われた。だが現在、神代医師は抗癌剤や放射線治療などの治療を行なっていないという。「『大細胞型』のがんは抗がん剤が効きにくく、放射線治療も効果がないんです。だから、もう対応のしようがない。飲んでいるのも胃腸薬ぐらいです。もちろん、自分がこれまで患者に言ってきたことと違うことをするわけにはいかないという思いもあります」
これまで彼は患者への治療を必要最小限にとどめてきた。それは延命ではなく“自分らしい人生”を送ることに重点を置いた治療だった。神代医師によると、今の医療はやるべき治療を行なっていない一方で、やり過ぎだと思うことも多いという。「もちろん何でも放置すればいいというわけではないですよ。でも手遅れなのに手術を重ね、辛い治療を続けることで“最期の時間”を犠牲にしている人も多いんです」
そんな彼が20年間に渡り提唱してきたのが『完成期医療福祉』という考え方だ。「『死ぬことはこの世から消えてしまうこと』だと考えると耐えられないほど恐ろしい。でも『死は人生を完成させるもの』と思えば、怖くなくなる。つまり充実した最期をもって人生を完成させるということです。そのためには、管理された病院で死ぬのではなく、自宅などの自由でいられる場所で最期をすごす必要があるんです」
患者のために人生を捧げてきた神代医師の考える“人生の完成”。それは、独居老人が自宅に戻って充実した最期を迎えるにはどうすればいいのか。どんなサポートが必要なのかという答えを見つけることだった。「幸か不幸か、私はがんになりました。だから自らが実験台となり、それらを見極めたいと思うようになりました」
しかし、今年2月に脳への転移が発覚。“独居闘病生活”の試みは、断念せざるをえなくなったという。理想と現実の間で揺れ動く神代医師は、しみじみとこう語る。「今回、私は2度の手術をしましたが、これでよかったのかなと思うこともあります。でもそれは最期にならないと誰にもわかりません。医者といっても神や仏じゃなく、人間ですから。何がよかったかなんて最期までわからない。そんなもんです」
そんな神代医師を支えているのは、家族の存在だ。妻の実津子さん(58)がこう振り返る。「今回の独居をいちばん反対したのは、27歳になるひとり娘でした。『なんで最期なのにパパと一緒にいられないの!最期はパパと一緒にいたい』と強く反対したんです。主人は子煩悩でしたからね。その言葉も心に響いたようです」
夫を元気づけようと、実津子さんは日本舞踏の仕事を辞め、夫の介護に専念することを決意。神代医師はいま、妻の作ってくれる手料理を何よりの楽しみにしているという。実津子が続ける。「普段は毎日料理をつくるのなんて疲れると思うはずですけど、今は不思議と楽しいんです。体調がいいときは一緒にお酒も飲んだりするんですよ。もちろん、ほんの少しですけど(笑)。こんな生活は、病院だとできないでしょうね」
神代医師は『いざとなっても救急車を呼ぶな』と実津子さんに言い聞かせているという。実津子さんは、笑顔でこう語る。「実は24時間ずっと主人が家にいる生活なんて、結婚して30年で初めてのことなんです。がんになったのは残念ですが、その反面、いま初めて主人がいつも家にいる。娘にすれば『パパがいる』生活なんです。きっと神様が最期に幸せな時間を与えてくださったんじゃないでしょうか。そう思うようにしています」