老老介護の地獄絵
夏場から、父は夜間せん妄が激しくなった。戦争体験からくると思われる夢にうなされ、部屋の中に敵がいると叫び、窓ガラスや鏡を自分の拳で粉砕した。止める母を殴り眼底骨折にまで追いやった。精神安定剤なしでは夜を過ごせないようになり、日中は片時も母のそばを離せなくなった。これが、元来、社交的で友達づきあいが何より元気の素であった母には堪えた。
母が救急車で担ぎこまれる件があってから通いはじめた医療機関では、アルツハイマーの進行する父と二人っきりの生活こそが、母の最大のリスクだと指摘された。私の考えと完全に合致したため、この医療機関に継続してお世話になることを決めた。
一旦はできるところまで自分でやってみる、父さんとふたりでやってみる、と踏ん張った母ではあったが、もう死にたいとまで言うところまで来てしまった。何が母を苦しめたかと言うと、徘徊である。家のなかで自分を叩いたり、モノを壊すのはまだ我慢できる。しかし、近所の家や警察の厄介になるようになると、もう惨めで情けなくてダメだ。そう言って母は涙を流した。
兼ねてより計画しては立ち消えになっていた、介護保険サービスの利用を開始した。ホームヘルパーが家に上がりこんでくることを良しとしなかった母と協議を繰り返した結果、ようやくのことでデイサービス(通所介護)とショートステイの利用に踏み切った。とにもかくにも、父を母から離すことで、一日のうち何時間かでも母を介護から解放してやることが目的だ。週1日から始め、徐々に回数を増やしていった。デイサービスに出かけた日の夜は、父もぐっすりと眠るようになった。
しかしながら、父の認知症は確実に進行し、クリスマスの頃には、母を市役所の職員と呼んだり、すでに亡くなっている父の姉と呼ぶようになった。そして、あれほど好きだった時代劇や西部劇のビデオを見ることもなくなり、部屋にいる時はボーッと天井を見つめているだけといった状態になっていった。この時点でまだ救いがあったとすれば、食事のみならず、排泄まで自力でできていたことだ。
ひとによって頻度や間隔がまちまちな排泄がコントロールできなくなったら、自宅での療養は不可能、というのが私の見解だ。排泄に介助が必要となれば、家族はおちおち眠ってはいられないのだ。なるべくならば家で介護をしてあげたいという母の希望に目をつぶっていたのだが、ついに、この年の11月、母からギブアップのSOSが入った。決断を下さなければならない時が訪れた。母を救うか、共倒れさせるか、である。
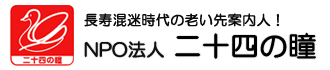

トラックバック URL
コメント & トラックバック/ピンバック
コメントはまだありません。
コメント