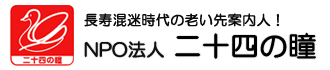感動する医者の話19
結果的に彼女は、わたしのもとへ週一回通院しながら治療することを選択されました。活性酸素を除くための点滴、プラセンタ注射、温熱療法を毎週1回受けに来ています。併せて、ペイスト状の玄米を主体とした食事療法も行っています。もともと胃が弱い体質だということで、漢方薬は出していません。これによってがんが退縮するかどうか、近日中に検査を受けてもらおうと計画しています。
がん患者さんに対する現代西洋医学の課題を示す例は他にもあります。例えばこんなケースがありました。ご主人(84歳)が、精密検査の結果、末期の大腸がんと診断され、慌てふためいて飛び込んでこられた女性がいました。一年前に自治体で受けた検診では異常なしだったにもかかわらず、です。すぐに摘出すれば成功の確率はほぼ100%だと言われたらしいのですが、当のご主人は手術だけは死んでもイヤだと言う。そこでご主人と会って話してみると、本人は痛くも痒くもないそうです。84歳。日常生活の支障はまったくない。術後の人生のことまで含めて考えたら、どう考えても摘出手術のリスクのほうが高いに決まっています。私は、手術は死んでもイヤというご主人の直感は当っている可能性が高いように感じると伝えました。
基本的に外科医というのは、がんにはまず手術という習性があるものです。なぜならば、「身体に悪いところがあれば切り取るのが外科医の仕事。手術はがん治療のプロフェッショナル・スタンダードで、がんと診断しておきながら何もしないというのは外科医の倫理に悖る」という教育を長きに渡り受けてきたからです。だから外科医は“取れるがんは取る”し、何も知らない患者側ももちろん、“がん治療の第一選択肢は手術”と信じて疑うことはありません。しかし、言ってみればこれこそまさしくEBMとは対極の理屈だと思いませんか。
(続)