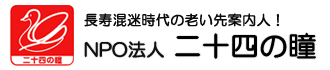こんな医者を探せ
患者の心得
ここで定義した健康や幸福を実現するために医者に求めるべきことは、実は患者の病気を治してくれることではない。そもそも医者には糖尿病も高血圧症も高脂血症も治せやしないのだから。医者にできるのは、血圧や尿酸値やコレステロール等を薬でコントロールするといった場当たり的な対症療法で、症状が改善したかのように錯覚させることだけである。
延命治療
終末期医療で、家族が「一分一秒でも長く」と要望したとしたら、カウンターショック(電気ショック)が1回35,000円、24時間対応心電図モニターが1日1,500円。人工呼吸器装着のために必要な気管内挿管措置は1日5,000円、人工呼吸器は1日12,000円。強心剤の点滴は1本7,000円、心臓マッサージは1回2,500円…(いずれも2010年現在)。差額ベッド代を除き、自己負担額は概ね2割前後ではあるが、平常心を失った状態のなかで、延命治療に係る費用が日々膨れ上がっていく。ホント驚くほどに…。500万円とか1,000万円とかいう金額もあっという間だ。また、延命措置に際して、患者側が求めない限り見積書は出てこない。医者の世界には事前見積りという考え方が定着していない。日本人はもう少し、欧米人のようにお金というものにシビアになったほうがいいのではないか。そして、ほんの数日間命を引き延ばすために患者に苦痛を強いるということの是非について、もっと考えるべきだと思う。
手術
もうひとつ。77歳の女性が肝臓がんと宣告された。転移もひどく末期とのこと。しかしながら本人には何の自覚症状もなく、1年前の検査では異常なしだったという。相談していただいた時点で一切苦痛がないということなので、ちょっとじっくりと考えましょうということにした。そして、まずはセカンドオピニオン。これだけの重篤な診断結果だ。複数の専門医の見解を聞かずして手術するなどはもってのほかである。セカンドオピニオンの結果、末期がんであることが確定したが、次は治療法の選択である。これが相談者の今後の人生にとっての分岐点になる。結果的に、手術を勧めた医者が3人、手術反対が2人。最終的に彼女が選択したのは、こう伝えた医者の意見であった。「年齢的なことや広範囲への転移を考えると、まず摘出手術は絶対に避けるべきかと思う。例え手術が成功しても後々の生活がキツい筈。術後の放射線照射や抗がん剤投与は、いずれも非常につらい副作用の覚悟が必要になる。何より気分が悪くてどうしようもない場合が多い。現時点で痛みがないのであれば、そんなリスクを犯す必要もない。私のお袋であったらそう言います」。
退院
交渉相手の内訳は、大学の附属病院、300床程度の民間病院、100床未満の民間病院である。こちらから先方に話した内容はほぼ一緒で、①本人またはご家族が抱いている不安 ②その上で退院時期の再調整依頼 ③転院先医療機関の紹介依頼 の3点。で、驚いたのは、3人の担当者が異口同音に「どうにもならない。また、転院先についても患者さん側で探してほしい」と回答してきたことだった。いゃあ、本当に驚いた。相手をしてくれた職員は、いずれも地域連携部門(正式名称は、地域連携室、医療福祉相談室)のスタッフである。
私は怒りを通りこして呆れながら尋ねた。
わかりやすく言うと、「これからは来た患者さんを何でもかんでも診るのではなく、自分の病医院がもっとも得意とする分野だけに特化しなさい。本来の守備範囲以外の患者さんは、地域の然るべき医療機関に渡しましょう。でもそうすると、これまではひとつの病院内での申し送りで済んでいたものが、別組織とのやりとりが必要になりますね。だから、患者さんに対する医療や介護の質が落ちないように、引渡しを円滑にする役割を担う組織を用意して、退院・転院する患者さんをサポートしてあげてくださいね」ということなのだ。これを受けて、その当時から、病医院のなかに『地域連携室』的な組織が続々と誕生してきて今日に至っているのである。
入院
高齢者患者のみならず、その家族たちもちょっとしたことで彼らに医者通いを奨励する。下手に家で倒れ、そのまま寝たきりにでもなられた日には、生活や人生そのものが変わってしまうからだ。冬場にちょっと咳ばらいでもしようものなら、医者と家族が示し合わせたように、当の本人がいくら大丈夫だと言おうが、『家だと冷えるから病院で過ごしたほうがいいわよ』とか、『万一のことがあってからでは遅いから』とか…。
こんな光景は全国で日常茶飯事である。厄介者を体よく追い出して、忙しくも賑わいのある年の瀬の準備に専念できるというものだ。で、入院させられたほうは、本当に身体を壊してしまったりする。なぜなら、病医院の中ほど病気になりやすい場所はないからだ。ただでさえちょっとした環境変化で体調を崩しやすい高齢者を病原菌の宝庫放り込むのだ。感染確率はかなり高いはずだ。家族は一瞬ギョッとするが、医者にしてみればまさに思う壺。その患者が死ぬまで貴重な収益源になる。国家的には国民医療費が膨れあがっていく…。
いかがだろうか? 例えばこんな会話を、医者が外部の人間である私と一献傾けながらするわけだ。高齢者患者の家族や病医院を侮辱するにも程があると不快感を露にする人もいるかも知れない。が、これが真実だ。ここまで露骨に言動に表すかどうかは別にして、本質は一緒である。紅葉が終わりに近づき年の瀬が迫ってくると、医者は空きベッドを埋めることに躍起になる。誤解を恐れずに言ってしまえば、無理やりでも埋める。それが彼らの仕事なのだ。経営とはそういうものなだから仕方ない。
そして、検査結果に異常がなければ、それっきり医者とは距離を置くことをお薦めする。あなたを引き留めるために、医者は『薬を出しておきましょう』、『しばらく様子を見ましょう』、『来週また来てください』などと言うだろう。しかし、もうおわかりだろう。医者の関心はあなたの健康ではなく、あなたが運んでくれるお金(診療の対価としてもたらされる医業収益)なのだから。もうそろそろ、自分や家族の健康を代償にしてまで医者の儲けに加担する愚に気づくときではないか。
カルテ
カルテ(正式には「診療録」)とは、客観的な事柄を記録として残しておくための文書であり、よって、誰が見ても読み取れるよう、記載者にしかわからないような略語や略字は使用できないことになっている。また、責任所在を明らかにするため、記載者と記載年月日&時刻も記載しなければならない。もしもカルテの写しを入手する機会があったら、是非ともこれらの項目が判読しやすく記載されているかどうかをチェックしてみて欲しい。
もうひとつ知っておいて欲しいことがある。それは、患者から請求された場合、医者には、正当な理由がない限り、診断書を作成して交付する義務があるということ。ちなみに、正当な理由とは、患者以外から請求されて患者のプライバシーが侵害される恐れがある場合、未告知のがん患者の場合、保険金詐欺等に悪用されることを医師が知った場合 である。
●普通の医者 必要なことが漏れていたり、どうでもいいことが書かれていたりすることはあるが、まぁ何となく時系列的には記録が残っている。その病医院独特の略語等が使われていたり、誤字脱字が散見されたりするのはまぁご愛嬌か。カルテの写しが欲しいと申し出ると、一瞬たじろぐも、所定の申請書を書くように言われる。が、求められたら提示せざるを得ないという社会的ルールは一応認識できている。患者本人でなくとも、委任状があって身元確認が取れれば対応してくれる。
紹介(セカンドオピニオン)
つまり、どこの病院のどの医者のところへ出向きたいのかを決めた上で申し出ないと、主治医と仲のいい医者を紹介されて終わってしまうということだって実際にはあり得るのだ。患者自ら「セカンドオピニオン外来」を受け付けている病医院を探したり、テレビや本で知った「これは!」と思える医者との道筋をつけたり、それなりの努力が必要となることは知っておきたい。セカンドオピニオンは、日本ではなかなか普及していない。「主治医に失礼になるのでは」と思う患者が多いからだ。
逸見さんの死後、がんの専門医などの間で、逸見さんの治療をめぐって手術はすべきでなかったという議論などが捲き起こり、テレビやメディアでも多く取り上げられた。晴恵さんはその議論を地団太を踏みたい気持ちで見ていたという。「主人の場合は納得して亡くなったと思いたいし、あれこれほじくりかえすのも主人の本意ではないと思う。ただ、もし私ががんになったら、いろんな情報の中から納得できる選択をしたいとつくづく思った」と、晴恵さんは語っている。
実際問題として、医者から説明を受けても、情報も知識もない患者や家族にとっては、治療法の決定をできないのはもちろん、恐怖や不安を覚える場合もある。だからこそ、知識を持っている人=専門医に相談し、意見を聞くなかで意思決定したいと思うのは当然のことである。そう考えると、インフォームド・コンセントとセカンドオピニオンは車の「両輪」であって、「良い医者」であれば患者や家族とのコミュニケーションを通じ、この両輪を円滑に回していくことの大切さを心得ていて然るべきである。
薬の処方
しかしながら巷の医者の多くは、そんなことお構いなしで薬を処方しまくっているのではないか。本当に患者を健康にしてあげたいと思う医者ならば、基本的に薬は服用しないほうがいいことを正直に伝えて欲しいものだ。やむなく薬を出す場合には、その必要性や飲み方やリスクについて、医者はキッチリと説明すべきである。不必要な薬を出すだけならまだしも、その薬の副作用で本当に深刻な状況を作り出してしまうことだってあるのだから。知り合いの医者仲間にも高血圧だったり糖尿だったりする人はかなりいる。でも彼らは、患者には薬を出しても、自分では薬を飲まず、食事や運動で少しずつ改善していると口を揃える。真実というのは、いつの時代もこういうものなのかもしれない。知らぬは善人(国民?)ばかりなり、である。
よくありがちな診察風景ではある。が、これではどこをどう判断して風邪と診断されたのかがまったくわからない。当の医者も「当たるも八卦、当たらぬも八卦」といった感じなのだろう。まぁ、この程度の稚拙な診察であっても、9割の患者は数日寝ていれば治るだろう。怖いのは、実は単なる風邪ではなかった…という場合である。また、患者が訴えるすべての症状ごとに対応して薬を出す医者は要注意だ。決して、「まぁ、なんて親切な」などと勘違いしないように。
薬というのはそれ自体が毒性を持っているものだし、薬相互の相性によって思わぬ副作用(死に至る場合さえある)をもたらすこともある。だから、良い医者というのは、患者と話し合いながら、いちばんつらい症状に配慮しながら優先順位をつけていくものなのだ。それと抗生物質。何かというとすぐに「抗生物質も出しておきますから」という医者がいまだに多い。抗生物質が風邪のウィルスに効かないという事実は周知の事実である。にもかかわらず抗生物質を出すのであれば、「ウィルス自体には有効性はありませんが、患者さんが高熱の場合に限って、感染症予防のために抗生物質を出すようにしています」などと、明確な説明が求められる。